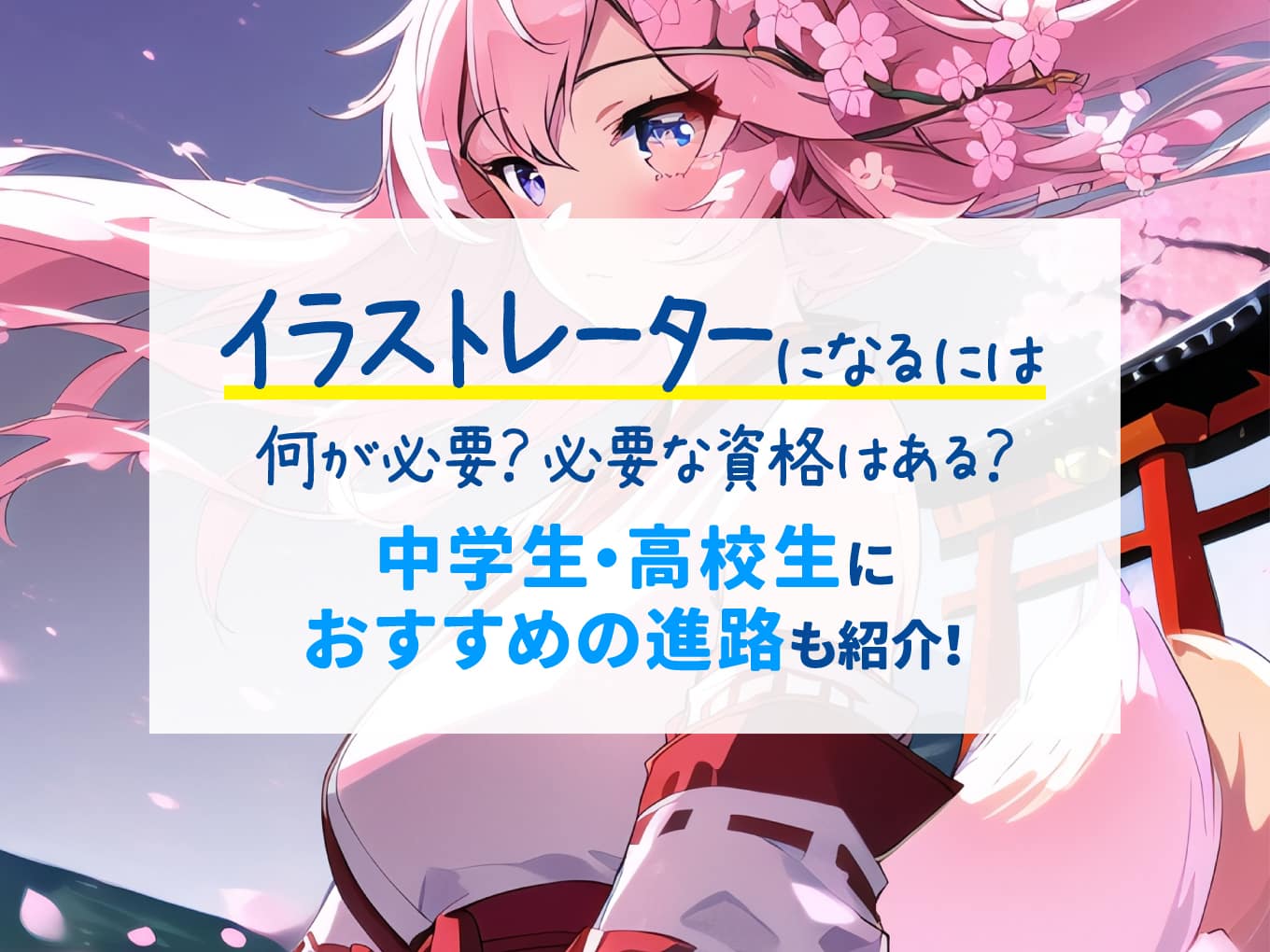
アニメや漫画などの影響を受け、イラストを描くことが好きで、将来イラストを仕事にできたらと思っている人は多いと思います。イラストレーターは、絵を通して感情やメッセージを伝え、人の心を動かすことのできる素敵な仕事。この記事では、イラストレーターになりたい中学生・高校生向けに、必要なスキルや仕事内容、おすすめの進路、そして若くしてイラストレーターになった先輩の声まで、具体的な情報を紹介していきます。(アニメーターになるには?の記事は >こちら )
イラストレーターの仕事内容とは?
イラストレーターの仕事は、主にクライアントの依頼に合わせてイラストを制作することです。自由に描くアーティストとは異なり、クライアントの要望を汲み取り、求められているイメージをイラストで表現します。幅広い分野で需要があるため、その仕事内容は様々ですがいくつかご紹介します。
書籍や雑誌などの表紙や挿絵
表紙イラストは、書籍や雑誌などの表紙に使用されるイラストです。使用される媒体の世界観を表現する役割があります。挿絵は、書籍や雑誌、新聞などの文章中に挿入されるイラストです。イラストが入ることで、読者のストーリーへの理解を助ける役割があります。どちらも出版社や編集部などから依頼を受けて制作します。
WEBサイトやパンフレットなどのイラスト
企業やショップのイメージアップ、PRなどのために、WEBサイトやパンフレットに使用されるイラストです。企業は、イラストレーターに依頼することで、ターゲット層に訴求力の高いイラストを作成し、企業や商品の認知度向上や販売促進につなげることができます。
ポスターのイラスト
屋内・屋外に関わらずあらゆる場所で目にするポスター。基本的に企業から依頼されますが、映画やイベント告知、商品の販促など業種や目的は様々です。クライアントの要望やターゲット層に合わせ、目の留まる魅力的なイラストを制作します。
商品パッケージのイラスト
商品パッケージは商品の外観であり、消費者の目に最初に触れる部分です。商品のコンセプトや特徴を伝えるだけでなく、消費者ターゲットに合わせ、手に取ってもらえるパッケージデザインが求められます。消費者の興味を引くためにイラストを使用する場合もあり、そのイラストを企業などから依頼を受け制作します。
ゲームのキャラクターや背景イラスト
テレビゲームやソーシャルゲームに必要なイラストは、ゲームに登場するキャラクターやアイテム、背景イラストなど様々です。ゲームの世界観に合わせたイラストやデザインの制作が求められます。近年はとくにソーシャルゲームの普及が非常に進んでいるため、イラストレーターの需要も高まっています。
SNSなどで使われるアバターのキャラクターデザイン
YouTubeを含むSNSなどで使われるアバターのキャラクターデザインは、ユーザーが仮想空間などでの交流やアクティビティを楽しむための重要な要素です。イラストレーターはアバターデザイナーの役割を担い、アバターの外見(顔、体、服装、アクセサリーなど)を制作します。3Dの要素が求められる場合には、3Dソフトを使える必要があります。
LINEスタンプ制作など
トークアプリLINEのスタンプは、「クリエイターズスタンプ」としてオリジナルスタンプを制作し、販売することができます。イラストレーターは、スタンプの企画から制作、審査申請まで、幅広い業務を担当します。また、個人でも制作・販売できるため、フリーランスや副業の方にも人気です。
工業製品や医療などのマニュアルに掲載するイラスト
工業製品や医療などのマニュアルに掲載する図柄やイラスト制作は、専門知識と技術を必要とする分野で、テクニカルイラストレーターやメディカルイラストレーターと呼ばれています。製品や医療器具の使用方法、構造などを視覚的に分かりやすく伝えるために制作されています。
このように生活のあらゆる場面で、ユーザーの興味を惹きつけるためや理解を深めるために、イラストが使用されていることがわかります。自分の描きたいものを描くのではなく、求められているものを描くのがイラストレーターの仕事です。
イラストレーターの働き方は?
イラストレーターの働き方は、大きく分けて正社員とフリーランスの2つのタイプと言われていますが、最近では副業としてイラストレーターをはじめる人も増えています。
正社員(デザイン会社やゲーム会社など)
正社員の場合は、デザイン会社やゲーム会社、広告代理店などに所属し、クライアントから依頼を受けてイラストを制作します。企業に所属するため、給与や待遇、勤務時間が安定していることや、大きなプロジェクトに参加できることなどが魅力です。また、企業ではパソコンを使用したイラスト制作がほとんどなので、デジタルソフトの操作スキルが高まります。企業によっては、イラスト制作以外の仕事も兼業となり、グラフィックデザインやレイアウト、販促物のプランニングなど、様々な経験を積むことができます。

フリーランス
フリーランスは、個人事業主として直接クライアントから仕事を請け負います。自分で仕事を選び、スケジュールも柔軟に組めるという利点がありますが、収入が不安定なこと、そして仕事獲得のための営業活動や経理業務なども自分でこなす労力が発生します。また、フリーランスで活躍するには、イラストに独自の世界観があると強みになります。「このテイストのイラストならあの人に頼もう」とクライアントの頭に浮かぶような印象に残るイラストは、仕事受注の面で有利に働きます。基本的には企業で経験値を高めたのちに、フリーランスになる人が多いです。

副業
副業のイラストレーターは、会社勤めをしながら隙間時間でイラスト制作を行う仕事のスタイルです。デジタル化が進んだ近年は、PCやタブレットがあればどこでも仕事ができるため、副業のイラストレーターも増えています。イラストの受注は、SNSやクラウドソーシングサイト、イラスト販売サイトなどを活用することで獲得できます。また、LINEスタンプやオリジナルグッズ販売などの稼ぎ方もあります。
イラストレーターの仕事の流れは?
クライアントから受注後のイラストレーターの基本的な仕事の流れをご紹介します。もちろん案件により多少の違いはありますが、主に以下のような流れとなります。
打合せ
クライアントと打ち合わせを行い、イラストの画風やイメージ、使用目的、使用媒体、サイズなど、イラスト制作に必要な情報をヒアリングします。また、納期、予算などを確認します。
ラフ作成
打ち合わせで確認した内容をもとに、ラフ(下書き)を作成します。ラフは、クライアントのイメージに合っているか、構図や絵柄が適切かを確認するためのものです。最終的なイラスト制作前の下書きのため、鉛筆などで描きます。
ラフの修正
クライアントにラフを確認してもらい、修正指示があれば修正を行います。修正は何度か繰り返すこともあります。
イラスト制作
クライアントの確認が済んだラフをもとに、最終的なイラストを制作します。イラストの線の太さや強弱を調整して清書したり、着色して魅力的なイラストに仕上げます。着色の前に一度確認に出す場合もあります。水彩やパステル、アルコールマーカーなど様々な画材で制作するアナログイラストや、デジタルソフトで制作するデジタルイラストなど、案件により手法は様々ですが、最近はデジタルイラストが主流となっています。
納品
完成したイラストをクライアントに提出し、修正指示や追加作業があれば対応し、完成したら納品します。JPEGなどの画像データで納品するのが一般的ですが、アナログイラストの場合、実際の原稿を納品する場合もあります。
イラストレーターになるには資格が必要?
イラストレーターになるために資格は必要ありません、イラストの画力とデジタルスキルが必要です。就職時に資格を求められることはほとんどありませんが、スキルの証明に使うこともできますので、個人でも受験できる資格をご紹介します。
Illustrator®クリエイター能力認定試験
Illustrator®クリエイター能力認定試験は、イラストレーターに必須のソフトのひとつIllustratorの操作スキルとクリエイティブな制作能力を測定・評価する資格検定試験です。株式会社サーティファイが主催・実施しており、実技試験のみのスタンダード、実技試験と知識試験のエキスパートの2つに分かれています。
Photoshop®クリエイター能力認定試験
Photoshop®クリエイター能力認定試験は、Illustratorと同様にイラストレーターに必須のソフトであるPhotoshopの画像処理や編集能力などを測定・評価する資格検定試験です。株式会社サーティファイが主催・実施しており、基本的な操作スキルを認定するスタンダード、応用的な操作スキルとデザイン知識を認定するエキスパートの2つに分かれています。
CGクリエイター検定
CGクリエーター試験は、CGで表現するデザイナー、クリエイターのための検定で、アニメーション実技試験と同様にCG-ARTS(公益社団法人画像情報教育振興協会)が主催。デザインや2次元CGの基礎から、構図やカメラワークなどの映像制作の基本、 モデリングやアニメーションなどの3次元CG制作の手法やワークフローまで、 多様な知識が出題されます。知識の理解を測る「ベーシック」と知識を応用する力を測る「エキスパート」に分かれています。
カラーコーディネーター検定試験®
カラーコーディネーター検定試験は、東京商工会議所が実施する検定試験で、色に関する知識や技能を問うものです。アドバンスクラスとスタンダードクラスの2つに分かれており、マークシート方式の多肢選択問題で出題されます。主に色の性質や特性、色の持つ効果をビジネスシーンで活かすための実践的な知識を習得できる検定です。
色彩検定®
色彩検定®は、公益社団法人の色彩検定協会が主催・認定する、色に関する幅広い知識や技能を問う検定試験です。1級から3級までの3段階に分かれおり、公式テキストに準拠した内容で出題され、色彩やデザインについての専門的な知識や実務経験は必要ありません。センスやアイデアを問うものではなく、公式テキストの内容をしっかりと理解すれば、これまで色彩を学んだ経験のない方でも合格できる検定です。
アドビ認定プロフェッショナル(ACE)
アドビ認定プロフェッショナル(ACE)は、IllustratorやPhotoshopなどのアプリケーションごとに専門知識とスキルを証明する資格です。2021年6月にアドビ公認アソシエイトからアドビ認定プロフェッショナル(ACE)に名称変更されました。ACEは、より高度な知識とスキルが求められる試験で、アソシエイトよりも難易度が高いとされています。
イラストレーターになるために必要なスキルは?
イラストレーターになるためには、画力やデジタルソフトのスキルはもちろん、独自性、コミュニケーション能力など、様々なスキルが必要です。プロとして活躍するのに求められる、主なスキルについて解説します。
デッサン力(基礎画力)
イラストレーターにとってデッサン力(基礎画力)は非常に重要です。デッサンは、人物や物体の形状、構造、陰影を正確に捉え、立体感を表現するための基礎的な画力であり、キャラクターや背景の自然な動きやポーズ、物の質感を表現する際に不可欠です。リアル系や劇画調、デフォルメ、カートゥーンなど、様々なイラストが存在しますが、どれも頭の中で思い描いたイメージを具現化するために、基礎であるデッサン力の習得は必須です。
デジタルソフトの操作能力
プロのイラストレーターに使われている主なデジタルソフトは、Photoshop、Illustrator、CLIP STUDIO PAINTです。これらのソフトを使いこなすことで、デジタルイラストの作成や編集、データ形式の変換など、イラストレーターとしての作業を効率的に行うことができます。その他、3DCGのキャラクターなどを描きたい場合は、3Dモデリングソフトなどの習得が必要です。どのソフトも数多くのツールが設定されており、非常に幅広い表現が可能となります。すべてをマスターする必要はないため、イラスト制作に必要な実践的な操作方法を学べる学校などで、専門的に教わったほうが習得は早く効率的です。
独自性の追求
イラストの独自性(オリジナリティ)はとても大切です。自分にしか描けないイラストは、他のイラストレーターとの差別化を図り、クライアントの印象に残ることで継続した仕事獲得にもつながります。イラストレーターは画力だけでなく、独自の表現力や世界観で、個性を際立たせることへの工夫が必要です。
依頼の意図を読み取る理解力
イラスト制作のうえで、理解力は必要不可欠なスキルです。クライアントの要望を的確に把握し、それをイラストに落とし込むためです。クライアントのイメージを理解し具現化するためには、イラスト自体だけでなく、作品全体のコンセプトや使用目的、ターゲット層を理解する力が求められます。
コミュニケーション能力
クライアントと打ち合わせなどの際、理解力だけでなく、円滑なコミュニケーション能力も必要となります。イメージが湧きにくい要望が出た際に、深く理解できるよう質問をしたり、参考のイラストを提示したりと、イメージを引き出せるよう、コミュニケーションを重ねる必要があるためです。また、スケジュール調整や修正などでもクライアントとのやり取りが発生しますので、円滑なコミュニケーションをとれる人が望ましいです。
アイディア・表現力
創造性の高いアイディアを生み出し、それを表現できるイラストレーターは重宝されます。同じ案件でも、他のイラストレーターとは異なる視点でアイディアを生み出す力があれば、クライアントからの期待も高まります。優れたイラストレーターの作品をたくさん見たり、現在のイラストやデザインのトレンドを把握し、アイディアの引き出しを増やす努力が必要です。
著作権への理解
著作権は創作物を保護する権利で、イラストレーターが描いたイラストや、漫画、絵本などの著作物に対して発生します。自分の制作したイラストでも、著作権をクライアントに譲った場合は、自由に使用することができません。自分の作品の権利を守り、他者の作品を無断で使用しないようにするため、著作権の基礎知識を理解しておく必要があります。

イラストレーターに向いているのはどんな人?
イラストレーターになりたいけれど、自分がなれるのか不安な人もいると思います。イラストレーターに向いている人の適性をまとめましたので、参考にしてみてください。
イラストが好きな人
何よりイラストを描くのが好きという気持ちが大切です。そして、絵を通じて何かを伝えたい、社会に貢献したいという熱意を持っている人が向いています。自分のイラストが商品や作品として世の中に出た際は、大きな喜びを得られるでしょう。また、自分の作品が評価されたり、クライアントに喜んでもらったりすると、大きな達成感と充実感を得ることができます。
コミュニケーション能力がある人
クライアントの要望を正確に理解し、単に要望を聞くだけでなく、提案をしたり、説明をしたり、人と協力して物事を進めるのが好きな人が向いています。また、フリーランスであれば、料金などの交渉が必要になる場面もありますので、納得してもらえるように説明や交渉をすることに対して、慣れておくことが望ましいです。
独自性の追求など向上心のある人
クライアントやファンを魅了し続けるには、常に目新しいイラストを生み出していかなくてはなりません。独自性の追求やスキルを磨く努力は、評価を得たり、仕事の獲得にもつながる大切なことです。今の自分に満足せず、新しいものを見て学び、新しいことに挑戦する、向上心にあふれた人がイラストレーターに向いています。
柔軟性や想像力がある人
イラストレーターは、自分の独自性を活かしつつも、何よりクライアントのイメージを理解し、要望に応えることが大切です。理解しずらい指示が出た際も、想像力を働かせて着地点を導き出せる、柔軟な対応が必要です。イラストだけでなく、作品や商品全体の情報を頭に入れ、考え方の面でも、技術面でも、臨機応変に対応できる柔軟性のある人が適任です。
責任感がある人
クライアントの期待に応え、納期を守り、高品質な作品を納品するために、責任感は不可欠です。なかでも納期は重要です。イラスト納品後に、他の人のデザイン作業などが続く場合が多く、全体の進行を妨げることのないよう、納期は厳守しなければなりません。とくにフリーランスの場合は、自身でスケジュール管理などを行う責任感のある人が向いています。

イラストレーターになるために中学生・高校生からできることは?
現在趣味の範囲でイラストを描いている中学生や高校生は、イラストレーターに必要なスキルを今から意識し、できることから行動に移すことが大切です。取り組む環境が整っていない場合は、自宅でできる範囲のことから実践したり、学べる場所を検討したりしてみましょう。
デッサンなど絵の基礎を学ぶ(画力の向上)
デッサンを学ぶことで、観察力や空間認識能力が向上し、イラストの表現力を高めることができます。リアルな描写だけでなく、イラスト特有の表現方法を学ぶためにも必要です。解説動画などを見て独学で練習してみるのもよいですが、絵画スクールや芸術系の高校などで学ぶことで、より効率的にスキルアップを図ることができます。
絵を描く習慣をつける
絵を何度も描いて練習することで、イラスト力が上達します。 最初は鉛筆や紙といったアナログ画材で十分です。 らくがきや模写など、毎日少なくとも30分は絵を描く習慣をつけましょう。1ヶ月ごとに見比べてみると「絵が上手くなっている」と必ず実感できるはずです。
デジタルツールやソフトに触れる
デジタルツールやソフトに早くから触れておくと有利です。ただ、液晶タブレットやペンタブレットなどのデジタルツール、そしてIllustratorやPhotoshopなどの定番ソフトの用意が必要です。実践的な操作方法の習得も考えると、学習環境の整った芸術系の高校などで学ぶほうが効率的です。
コンテストやSNSなどで作品を発表する
制作したイラストを自分の中で完結せずに、他社の評価を求めましょう。コンテストへの応募は、専門家の評価を得られたりと、スキルアップや実績作りに役立ちます。中学生・高校生向けのコンテストも開催されていますので、情報をチェックしましょう。
また、SNSで作品を公開することで、より多くの人に自分の作品を見てもらう機会が増えます。多くの人から評価やコメントをもらうことで、自分の作品のレベルや改善点を知ることができたり、他のイラストレーターと交流し、意見交換などでモチベーションを高めたり、スキルアップにつなげることができます。
好きなイラストレーターやアーティストの作品を研究する
好きなイラストレーターやアーティストの作品について研究することは、自分の感性を磨き、表現の幅を広げるよい方法です。まずは興味のある作家や作品を深く知り、なぜその作品が魅力的なのかを分析してみましょう。さらに、真似をして描いてみること。模倣することで、基本的な技術を習得したり、他のアーティストの作風や手法を理解可能です。ただのコピーではなく、そこに自分のオリジナルな要素を加えたりと、たくさん試して描くことで、画力や表現力を磨きましょう。
イラストレーターになるために中学生・高校生におすすめの進路を紹介!
イラスト・芸術を専門的に学べる高校への進学がおすすめ
現在中学生・高校生の時点でイラストレーターになりたいと考えているのであれば、イラスト科やイラストコースがある芸術系の通信制高校がおすすめです。専門学校と同等の教育・設備が整う通信制高校なら、高校生という若いうちに、イラストに関する専門的なスキルや知識を習得することができます。専門学校より3年も早くスタートを切ることができるのは大きなメリットです。現在は通信制高校のように若くして学べる教育機関の増加や、SNSの普及による作品共有の容易さもあり、若いイラストレーターが増加しています。芸術分野はスキル習得が早ければ早いほど、大きな武器となります。
普通高校より多くの時間を絵を描くことに使える
専門科目が学びのメインとなる通信制高校では、週5日間のうちほとんどが絵画やイラスト制作など専門科目の授業になります。普通科目は登校せずにオンライン授業などを交えて短時間で習学するため、イラストに特化した授業に多くの時間を使えます。3年間を通して、絵画やイラストのプロから本格的な指導を受けることで、画力は飛躍的に向上します。また、通信制高校では全日制と同じ高校卒業資格の取得が可能なため、卒業後の進路も大きく開かれています。多くの通信制高校では普通科目のほか、絵に特化した専門科目も単位認定されます。
デッサンなど基礎からしっかり学べる
イラスト科/イラストコースがある通信制高校には、基礎画力を身につけるデッサンの授業が必ずあります。観察力や表現力を高め、より魅力的なイラストを描くための基礎を築くうえで、デッサンは非常に重要です。難しそうな印象を持っているかもしれませんが、高校の段階ではこれまで趣味でイラストを描いていて、本格的に学ぶのははじめての生徒がほとんどですので、デッサン初心者や未経験者でも安心です。初歩的な基礎からスタートし、段階を踏んで徐々に高度な技術を学んでいきます。

デジタルソフトの使い方を基礎から学び習得できる
現在はデジタルイラストを描くために、デジタルソフトの習得は不可欠です。イラスト科/イラストコースがある通信制高校には、パソコンやタブレットなどのデジタルデバイス、そしてIllustratorやPhotoshop、3DCGソフトなどのデジタルソフトを完備しています。もちろんデジタルイラストに触れるのははじめての生徒がほとんどですので、基礎からじっくりと実践的なことを学び、習得することができます。
マンガやアニメ、デザインなどについても学べる
イラスト科/イラストコースがある多くの通信制高校では、イラスト、マンガ、アニメ、デザインなど、幅広い分野の授業が用意されています。現役のプロによる実践的な指導で総合的なスキルを習得できるだけでなく、それぞれの業界知識などにも触れることができるため、高校生という若いうちに、自分の興味や適性に合わせた分野を見つけることができます。
進学や就職など卒業後の芸術分野への進路のサポートが充実している
専門的な教育を行っている通信制高校は、学校・先生方の進学・就職へのサポート体制が非常に整っていることも特徴です。業界とのつながりや採用情報などが充実しているため、全日制高校と比べて将来を具体的に考えやすい環境です。難関芸術大学・美術大学へ進学できることは芸術系の通信制高校の魅力ですし、進学だけでなく、就職という道を選ぶこともできるため、進路の選択肢は幅広いです。専門学校では2年しか学ぶことができませんが、通信制高校の魅力は、早期に3年間も専門的な勉強ができることです。3年間努力して実力をつければ、18歳でイラストレーターになることも夢ではありません。
実際に高校卒業後すぐにイラストレーターになった卒業生がいる
実際に高校卒業後の弱冠18歳で、幅広くデザイン、イラスト制作を取り扱っているデザイン会社に就職した、愛知芸術高等専修学校/名古屋キャンパスのマンガ・イラストコースの先輩の声をご紹介します。
『愛知芸術高等専修学校では、ほかではなかなかできない特別な経験をたくさんさせてもらいました。愛芸に入学していなければ、こんなに成長できなかったですし、コンテストに出品して入賞することもなかったと思います。充実した授業内容と、先生方の的確なアドバイスのおかげで、今があると思っています。クリエイティブな分野を仕事にするという夢を叶えた今、さらなる目標は、イラスト分野のみならず、愛芸の授業で学んだアニメーションの技術をより伸ばしていくということです。』
高校の3年間で飛躍的に画力を伸ばし、デジタルソフトの扱いに慣れたことで、自分らしい色彩や表現を手に入れた彼女の成長の様子は、以下の記事で詳しく紹介しています。ぜひご覧ください。
マンガ・イラストコースのあるおすすめ通信制高校「芸高グループ」
芸高グループは、学校法人恭敬学園が運営する北海道芸術高等学校をはじめとする、以下5つの学校(6つのキャンパス)で構成される、芸術分野の専門性に特化した学校です。
<芸高グループ>
北海道芸術高等学校
札幌サテライトキャンパス
東京池袋サテライトキャンパス
福岡芸術高等学校
東北芸術高等専修学校
横浜芸術高等専修学校
愛知芸術高等専修学校
マンガ・イラストコースは全てのキャンパスに設置されています。未経験でも初心者でも、自信がなくても大丈夫。「絵を描くのが好き、イラストレーターになりたい」という気持ちを重視しています。中学校卒業以上であれば入学に年齢制限はなく、いつでも転入学・編入学可能です。中学校卒業後の一般的な4月の入学のほか、現在高校に通っている人も高校を退学した人も、転入学・編入学できます。
6つのキャンパスのうち3つに関しては高等専修学校ですが、北海道芸術高等学校(通信制高校)とのダブルスクール制度を採用することで、全日制と同様の高校卒業資格の取得も可能となっています。そのため、進路の選択肢も広がっていますので、イラストレーターを目指して心置きなく絵を描くことに没頭できます。

✅ マンガ・イラストコースに関するこちらの記事もチェック
> 不登校でも高校に行ける!東京でイラスト・漫画を学んで成長できるおすすめ通信制高校
> マンガ・イラストコースではどんなことが学べるの?授業について教えて!(北海道芸術高等学校 札幌キャンパス編)
> アニメーターになるには?中学生・高校生からできることは?高校選びからおすすめの進路を紹介!
> プロ仕様の環境で学べる!施設・設備紹介(北海道芸術高等学校 札幌キャンパス編)生徒の口コミ・評判も!
💬 在校生や卒業生の声はこちら
>【在校生インタビュー:Mさん】作品と共に3年間の成長に迫る!(福岡芸術高等学校 マンガ・イラストコース編)
>【卒業生インタビュー:Yさん】大手アニメ制作会社に18歳で入社!就職活動や仕事について教えて!
>【卒業生インタビュー:Yさん】創業100年以上の老舗ゲーム開発会社に入社!進路活動や仕事について教えて!
>【卒業生インタビュー:Kさん】作品と共に3年間の成長に迫る!(北海道芸術高等学校 東京池袋キャンパス マンガ・イラストコース編)
好きなことだからがんばれる、一緒に歩んでくれる先生や仲間がいる。
芸高グループは、一人ひとりの個性や夢を応援してくれる場所です。
参照:北海道芸術高等学校 https://www.kyokei.ac.jp/
※本サイトは、芸高グループの生徒や先生にインタビューを行う機会をいただき、独自取材の記事で芸高グループを応援する個人運営サイトです。
> 生徒たちの様子がわかるInstagramはこちら
この記事をシェアする
