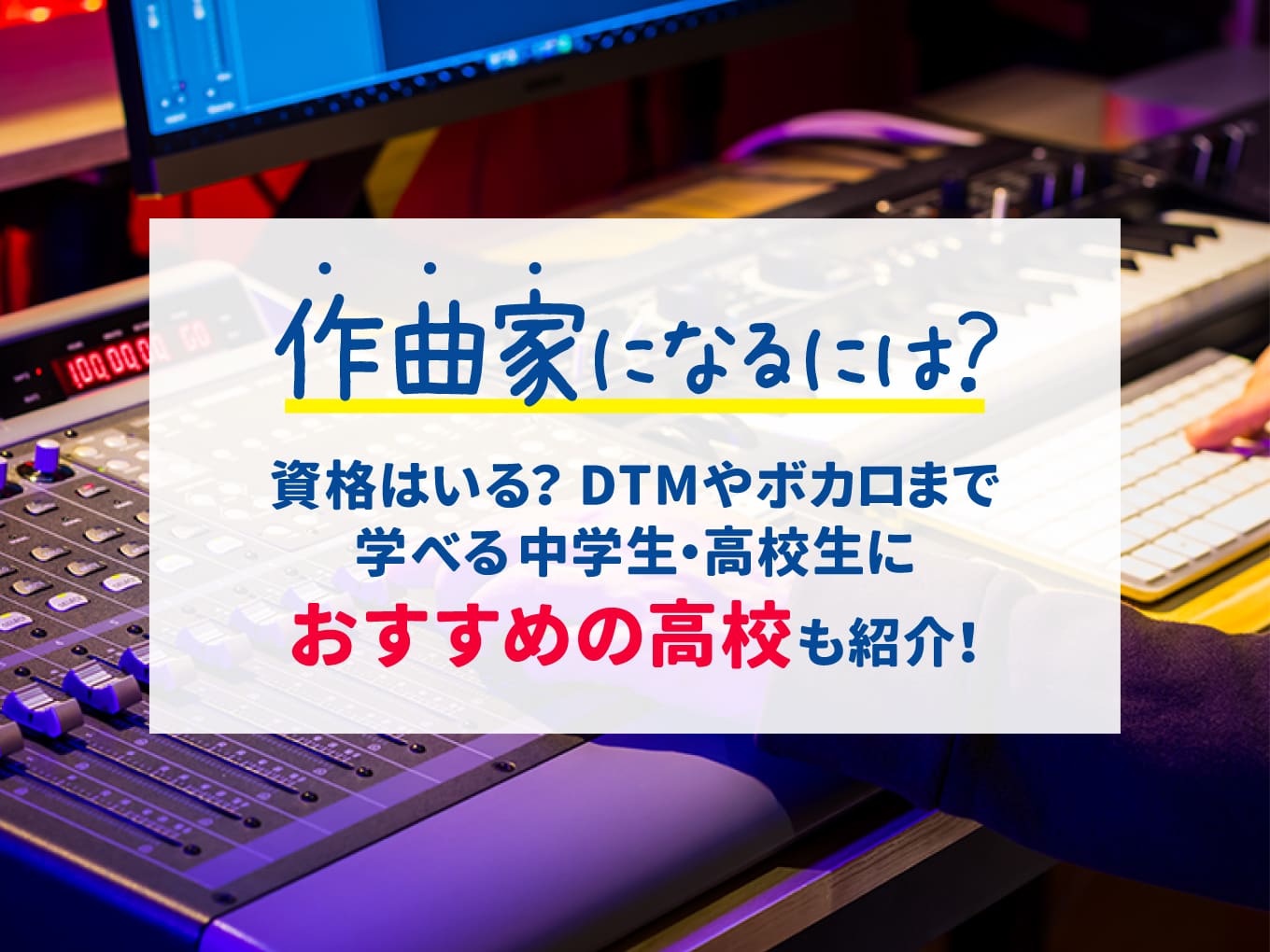
アーティストやアイドルへの楽曲提供をはじめ、アニソンの作曲家になりたいという若者も増えている作曲の世界。近年はSNSからのプロデビューも夢ではありません。この記事では作曲家になりたい中学生・高校生向けに、必要なスキルや仕事内容、作曲家への道のり、そしてDTMやボカロを学べるおすすめの高校まで、具体的な情報を紹介していきます。
作曲家の仕事内容は?
作曲家の仕事内容は、音楽のジャンルや制作範囲によって多岐に渡りますが、大きくは、歌謡曲やポップスなどを手掛ける「ソングライター」と、アニメやゲーム、映画音楽などを手掛ける「コンポーザー」に分類できます。
歌謡曲やポップスなどの作曲(ソングライター)
ソングライターは、歌謡曲やポップスなどの歌詞や曲(メロディ)を制作する作曲家です。いわゆる作詞・作曲ですが、作曲のみで音楽を提供し、アーティストが作詞を行う場合もあります。また、作詞・作曲した音楽を自分で歌うシンガーソングライターも、ソングライターの一種とされています。ソングライターは、企業やアーティストから依頼されて楽曲制作を行いますが、希望のアイドルやアーティストの作曲を手掛けたい場合は、レコード会社が主催するオーディションやコンクールに応募します。
アニソン、ゲーム、映画、ドラマ、CMなどの作曲(コンポーザー)
コンポーザーは、楽曲のメロディ、ハーモニー、リズムなどを構成する作曲家です。楽曲制作だけでなく、編曲、アレンジなど、音楽制作の様々な工程に関わることもあります。音楽のジャンルは様々で、アニメや映画、ドラマの主題歌やBGM、ゲームのBGMや効果音、CMのテーマ曲制作など。最近はDTMでの作曲が主流となっています。(DTMはパソコンを使った音楽制作のこと。スキル紹介で詳しく解説します。)
このように上記の2つに分類されますが、それぞれさらに細分化されていたり、兼業する場合もあります。また、プロデュースやレコーディング、プロモーション活動などに関わる場合があったりと、職場や業務によって、その仕事内容は大きく変わってきます。
作曲家の働き方は?
作曲家の働き方は、音楽事務所やレコード会社などの企業に所属するか、フリーランスとして活動するかの2つのタイプに分かれます。
音楽事務所やレコード会社など企業に所属
企業に所属する場合は、音楽事務所や芸能プロダクション、音響制作会社、レコード会社、ゲーム制作会社、アニメ制作会社などがあります。企業は仕事の窓口になってくれるため、フリーランスに比べて収入が安定し、事務所のネットワークを活用して、幅広い仕事に携わることができるのが魅力です。基本的には社員として就職する企業が多いですが、音楽事務所や芸能プロダクションのなかには、社員として雇用されるケースのほか、業務委託契約の場合があり、そうなると報酬は完全出来高制となります。
フリーランス
フリーランスとして活動する場合は、自分の好きなジャンルや仕事を選び、スケジュールも柔軟に組めるという利点がありますが、収入が不安定なこと、そして仕事獲得のための営業活動や経理業務なども自分でこなす労力が発生します。仕事を得るには、コンペ形式での楽曲制作や、完成した楽曲をSNSで発表するなどのプロモーションが必要です。基本的には、企業でその分野の専門家として経験値を高めたのちに、フリーランスになる人が多いです。なお、フリーランスは、ヒット曲を生み出せば収入が大きく伸び、夢の印税生活という可能性もあります。
作曲家になるための資格はある?
資格は必要ありません
作曲家になるために資格は必要ありません、音楽に関する知識や技術、そして音楽センスを磨くことが重要です。就職時に資格を求められることはありませんが、近年はDTMを活用して作曲することが多いため、MIDI検定などの資格を取得するとDTMのスキルを証明できます。
MIDI検定
MIDI検定は、一般社団法人音楽電子事業協会(AMEI)が主催する検定試験で、DTMや音楽制作に関わる人材育成を目的としています。4級から1級までがあり、4級は入門レベル、3級は基礎知識、2級は実務レベルで音楽制作に携わる人材、1級は音楽制作の実務者レベルと、段階的に知識を深めていくことができます。

作曲家になるにはどうしたらいい?なるための道のりは?
まずは学校などで音楽の基礎知識・作曲技術を身につける
作曲家になるためには、まずは芸術系の高校や専門学校、大学などで学び、音楽理論の知識や楽曲制作に必要な技術を身につけることが重要です。独学ではなく学校に通うことがおすすめの理由は、体系的な学習、プロの指導、業界との繋がり、そして仕事に活かせる実践的なスキル習得など、独学だけでは得られない数々のメリットがあるからです。
学校で実力を磨き、卒業後に作曲家を目指す道のりは以下のような方法があります。
①音楽事務所やゲーム会社など企業に所属する
企業に所属したい場合は、在学中に就職活動をしましょう。音楽事務所や芸能プロダクション、音響制作会社、レコード会社などが就職先となります。アニソンを制作したい人や、ゲーム音楽を手掛けたい人は、ゲーム制作会社やアニメ制作会社でも作曲家を募集しています。作曲家になるためには、音楽理論や作曲技術はもちろんですが、何よりセンスが重視される芸術の世界ですので、自身の個性を売り込むプロモーション能力なども高めておきましょう。
②レコード会社主催のオーディションやコンクールに応募する
レコード会社主催のオーディションやコンクールに応募することは、作曲家を目指すうえで有効な手段のひとつです。企業との契約のチャンスやプロデビューの足がかりとなります。アーティストの楽曲募集や賞金の出る大会など様々ですが、オーディションで実績を残せば、作曲家としてプロデビューするチャンスがあります。また、コンクールで作曲の実力や才能を発揮することができれば、レコード会社や音楽事務所に所属できる可能性もあります。はじめは予選落ちでも、学生のうちからオーディションやコンテストに応募して、経験を積むことが大切です。
③アーティストやミュージシャンとして活動し知名度を上げる
作曲家を目指しているが、楽器を演奏するのも好き、歌うのも好き、という人は、まずは音楽業界に飛び込んでみるのもひとつの手です。スタジオミュージシャンやライブミュージシャン、バックミュージシャン、そしてシンガーソングライターなどのアーティストとして活動を続けることで、人気や認知度が上がり、音楽関係者から声がかかることがあります。
また、ライブハウスのスタッフなどは、実力があれば音楽関係者との交流の場を提供してくれますので、プロの音楽関係者と交流する機会を増やしましょう。ライブで披露した曲が気に入ってもらえれば、あの子を試してみようと、仕事をもらえるかもしれません。一昔前のSNSが浸透する前は、このように現場で活躍していたギタリストやキーボーディストが作曲家になる流れも多く見られました。チャンスはどこに転がっているかわかりませんので、ライブやイベントに積極的に参加したり、人との出会いを大切にしましょう。
④SNSや動画サイトで楽曲を発表する
最近はDTM(パソコンを使った音楽制作)が主流となっており、そのなかでも歌声合成ソフトであるボカロを用いたボカロ曲は、歌い手がいなくても手軽に楽曲制作ができるため、YouTubeなどの動画配信サービスで発信され大きく広がりました。さらにTwitterなどのSNSを通じて、ボカロ曲のシェアや、ボカロPとのコミュニケーションが活発に行われ、ボカロ文化の広がりを加速させました。
このようにSNSで楽曲を公開することで、良い楽曲は瞬く間にシェアされ、話題になる可能性があります。ボカロ曲だけでなく、自身で歌った楽曲やバンド演奏など、SNSであれば幅広い層に楽曲を届け、認知度を高めることができます。また、音楽関係者のSNSアカウントをフォローし、交流を深めるためにコメントやDMを送ることもできます。自分の作品を積極的に発信し、音楽関係者と交流することで、デビューのきっかけとなったり、コラボレーションの機会を得ることなどができます。

作曲家になるために必要なスキルは?
作曲家になるためには、音楽の知識や楽曲制作のスキルはもちろん、スピードやコミュニケーション能力など、様々なスキルが必要です。プロとして活躍するのに求められる、主なスキルについて解説します。
音楽の基礎知識
プロの作曲家になるためには、音楽理論をはじめとする基礎知識の習得が必須です。音楽理論は、音の高さ、音程、リズム、コード、ハーモニーなど、音楽を構成する要素について、音楽の歴史や作法、楽曲の構成など、様々な角度から音楽の理解を深めます。そのほか、楽譜の読み書き、メロディーやコード進行、アレンジなどの作曲技術を身につけておく必要があります。また、DTMが主流となっても、ピアノやギターなどの楽器を演奏できると重宝されます。作曲の際にもアイデアがより具体的に表現しやすくなると言われています。音楽の基礎知識は、体系的に学習することのできる芸術系の高校や専門学校、大学などで学ぶことをおすすめします。
DAWソフトの操作などDTMの技術
DTMとは、Desktop Musicの略でパソコンを使った音楽制作を指します。楽器を演奏しなくても、マウス操作で音楽を作ることができます。ジャンルを問わず、作曲や編曲、録音、編集など、音楽制作のほとんどのプロセスをパソコンで行うことができるため、最近は音楽制作の主流となっています。DTMで作曲を行うには、DAW(Digital Audio Workstation)と呼ばれるソフトの操作が必須です。DAWソフトの機能を使いこなすことで、高品質でオリジナリティあふれる楽曲を生み出すことができます。なお、歌声合成ソフトであるボカロも、DTMの一種です。
時代に求められる音楽をつかむ好奇心・向上心
作曲家には、新しい音楽やトレンドを把握し、それに合わせた楽曲制作を行うスキルが求められます。その時に人気のあるジャンルや曲調を取り入れつつも、独自の要素を加えることが重要です。独自の要素は、知識や技術だけでなく、創造性やセンスによるものが大きいです。創造性やセンスを磨くために、常に好奇心を持って新しい音楽に触れ、ジャンルを問わず音楽を聴き、分析することで、徐々に自分の身につき、新しく独創的な音楽を作り出せるようになります。向上心を持って経験を重ね、自分にしか作り出せない音楽ができれば、評判は広がり、仕事のチャンスも増えます。
期間内で作曲するスピード
与えられた期間内で作曲するスピードは、プロの作曲家にとって不可欠です。とくにフリーランスであれば、納期を守ることは信頼性を築くために重要です。作曲のスピードは、経験や技術によって大きく左右されますが、インスピレーションが湧きやすい環境を整えたり、閃いたアイデアを音として表現できるよう様々な音楽に触れておく、また、DAWを使いこなして作業効率を向上させるなど、プロであれば自分の作曲のプロセスを整理し、効率的に魅力的な楽曲を仕上げることが求められます。デモ音源から曲を完成させるまでも時間を要するため、関係者にイメージを伝えるデモ音源の制作が早い作曲家は重宝されます。
依頼内容を汲み取るコミュニケーション能力
企業やアーティストから依頼されて楽曲を制作する場合、打ち合わせやクライアントとのやり取り、スタジオでの収録など、様々な場面で円滑な関係性を築くことのできるコミュニケーション能力が求められます。とくに、クライアントの依頼内容やイメージを汲み取るコミュニケーション能力は重要です。どんな雰囲気やジャンルの楽曲にしたいのか、どんなメッセージを伝えたいのかなど、具体的なイメージを引き出して理解できるスキルや感覚は非常に大切です。楽曲の方向性を正確に共有することで、クライアントの期待に応え、より良い楽曲を生み出すことができます。
作曲家に向いているのはどんな人?
音楽が好きで作曲家になりたいけれど、自分がなれるのか不安な人もいると思います。作曲家に向いている人の適性をまとめましたので、参考にしてみてください。
何より音楽が好きな人
まずは何より音楽が本当に好きで、音楽漬けの日々を楽しめることが大切です。毎日、複数の楽曲を制作する可能性もあるため、それをやりがいと感じて音楽と向き合える人が向いています。きっとこの記事を読んでいる人は当てはまると思います、常に音楽に触れ、自分の内なる音楽表現を追求する情熱は、必ず作曲の原動力となります。
好奇心・チャレンジ精神のある人
作曲家になるには、音楽への好奇心とチャレンジ精神が不可欠です。作曲家としての才能を磨くためには、自分の好みに合わせて音楽を聴くだけでなく、ジャンルを問わず様々な音楽に触れ、音楽を構成する要素や音の響きに意識を向け、分析して理解を深める好奇心が必要です。また、音楽のトレンドを把握し、常に時代の変化に合わせた楽曲を手がけることが求められるので、新しい作曲手法を積極的に取り入れる、チャレンジ精神旺盛な人が向いています。
根気強く楽曲を作成し発表できる人
作曲には時間と労力を要します。アイデアが閃かず悩むこともあるでしょうし、クライアントからのOKが出ず制作し直す場合もあるでしょう。どんな状況でも納得した楽曲が仕上がるまで、辛抱強く努力を続けられる人が向いています。また、仕事でもプライベートでも継続して楽曲を作成し発表し続けることが重要です。とくにフリーランスであれば、認知度が高まり人気がでれば、仕事に繋がる時代です。多くの楽曲を手がけることで、音楽センスも磨かれていきますので、根気強く、向上心を持って取り組む姿勢が大切です。
作曲のスピードが早い人
一説によると、多くの成功した作曲家は年間100曲以上のデモを制作するペースで曲作りに取り組んでいるとされています。そのすべてが完成する楽曲となるわけではないですし、1年間に数曲しか制作しない作曲家もいますが、ヒット曲を生み出すためには、作曲のスピードが早いほうが有利と言えます。SNSでオリジナル曲の配信からプロになった人も出てきている近年、作曲スピードが早ければその分SNSでも多く発表でき、ファンの獲得や音楽関係者から声がかかるチャンスも広がります。
楽器が弾ける人
最近はDTMを活用すれば、楽器が弾けなくても音楽制作が可能ですが、楽器を弾けることは作曲をするうえでプラスに働きます。楽器の演奏を通して楽曲の構成や表現方法を体験し、音やリズムをより深く理解できるようになりますし、作曲のアイデアも直接表現しやすいと言われています。そのほか作曲以外の活動の幅も広がるなど、メリットはたくさんあります。また、バンドやグループでの演奏経験は、豊かな感情や表現力を育んでくれます。何より仲間と奏でるグルーブ感は、何にも変え難い音楽の楽しさを体感できますので、ぜひ気になる楽器があれば挑戦してみましょう。
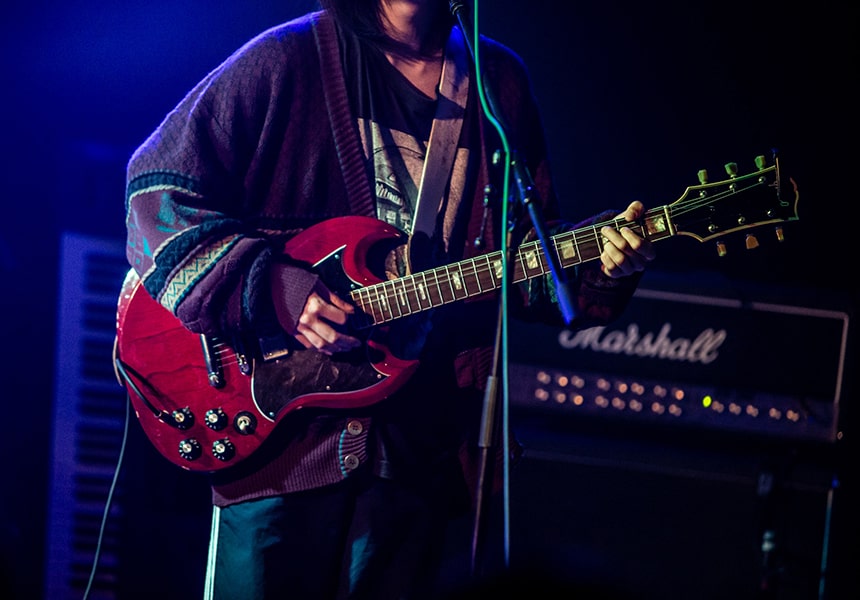
作曲家になりたい中学生・高校生におすすめの進路・高校を紹介!
人より早く音楽を学べる芸術系の高校に行くのがおすすめ
現在中学生・高校生の時点で作曲家になりたいと考えているのであれば、ミュージックコースや音楽科のある芸術系の通信制高校がおすすめです。専門学校と同等の教育・設備が整う通信制高校なら、高校生という若いうちに、音楽に関する専門的なスキルや知識を習得することができます。専門学校より3年も早くスタートを切ることができるのは大きなメリットです。現在はSNSの普及による楽曲共有の容易さもあり、若い作曲家やシンガーソングライターが活躍しています。高校生のうちにスキルも質も磨いて、チャンスを大きく広げましょう。
普通高校より多くの時間を音楽に触れることができる
専門科目が学びのメインとなる通信制高校では、週5日間のうちほとんどが音楽や作曲に関する専門科目の授業になります。普通科目は登校せずにオンライン授業などを交えて短時間で習学するため、音楽に特化した授業に多くの時間を使えます。例えば全日制高校の放課後に自己流で音楽ソフトをいじるのと、通信制高校で学校にいる時間に専門的に学ぶのと、練習量にも質にも歴然の差が出ます。また、通信制高校では全日制と同じ高校卒業資格の取得が可能なため、卒業後の進路も大きく開かれています。多くの通信制高校では普通科目のほか、音楽に特化した専門科目も単位認定されます。
プロから授業を受けられる
ミュージックコース/音楽科のある通信制高校なら、ほとんどの場合、講師を務めるのは現役で活躍するプロのミュージシャンや音楽関係者です。現場経験豊富な講師陣から、実践的な直接指導を受けられることは大きな魅力です。また、専門的な教育を行っている通信制高校では、音楽業界でのコネクションの作り方や人間関係の構築の仕方など、仕事に役立つ情報も授業で教わることができます。音楽業界で活躍しているプロによる貴重な授業は、音楽業界を身近に感じることができ、技術だけでなく世界観・発想力を広げてくれます。
初心者でも幅広く音楽の知識・技術を学ぶことができる
ミュージックコース/音楽科の授業内容は、学校により異なりますが基本的に、楽器演奏、歌唱法、作詞・作曲などの実技から、音楽理論や各種音楽のメソッド、業界知識まで、卒業後を見据えた幅広い知識・技術を学ぶ授業が用意されています。ライブやレコーディングなどの実習もあり、音楽業界を身近に感じる非常に実践的な授業が組まれています。多くの通信制高校では、初心者・未経験者も歓迎で、個々のレベルに合わせた丁寧な授業を行っています。楽器を持っていなくても大丈夫です、基礎からしっかり学んで成長できます。
DAWソフトの他、ボカロや動画制作について学べる学校もある
最近の作曲でも主流となっているDTMを活用した音楽制作を学ぶ授業は、ほとんどのミュージックコース/音楽科に用意されています。音楽制作ツール全般を指すDAWソフトを使用し、基本的な操作方法を学びます。レコーディングや作曲・編曲、打ち込みなどが可能なので、楽曲を完成させる流れ・技術を習得できます。また、今の時代、SNSなどでの楽曲発表も活動のひとつのため、動画制作などのスキルもあると役立ちます。DAWソフトだけでなく、歌声合成ソフトであるボカロや動画制作などの授業を用意している通信制高校もあります。
進学以外にも就職など卒業後の進路が幅広くサポートも充実している
専門的な教育を行っている通信制高校は、学校・先生方の進学・就職へのサポート体制が非常に整っていることも特徴です。業界とのつながりや採用情報などが充実しているため、全日制高校と比べて将来を具体的に考えやすい環境です。卒業後は大学・専門学校への進学だけでなく、就職という道を選ぶ人も多いため、進路の選択肢は幅広いです。専門学校では2年しか学ぶことができませんが、通信制高校の魅力は、早期に3年間専門的な勉強ができることです。しかも卒業時は弱冠18歳。若いうちに選択できること、様々な経験を積めることは非常に大きなメリットです。
設備が整っている
多くのミュージックコース/音楽科のある通信制高校には、実技の練習ができるミュージックスタジオが設置されています。ギターやドラムセットなどの楽器類をはじめ、照明機材も完備された防音のスタジオです。DTMでの音楽制作を行いやすい空間が用意されていたり、PA環境(音響システムによる快適な音環境)も整っていたりと、音楽全般の実習や業界の仕組みがわかる実践的な仕様のスタジオで、音楽に没頭した高校生活を過ごすことができます。

ミュージックコースのあるおすすめ通信制高校「芸高グループ」
芸高グループは、学校法人恭敬学園が運営する北海道芸術高等学校をはじめとする、以下5つの学校(6つのキャンパス)で構成される、芸術分野の専門性に特化した学校です。
<芸高グループ>
北海道芸術高等学校
札幌サテライトキャンパス
東京池袋サテライトキャンパス
福岡芸術高等学校
東北芸術高等専修学校
横浜芸術高等専修学校
愛知芸術高等専修学校
ミュージックコースは、北海道芸術高等学校/札幌キャンパス、東北芸術高等専修学校/仙台キャンパス、愛知芸術高等専修学校/名古屋キャンパスの3つのキャンパスに設置されています。未経験でも初心者でも、自信がなくても大丈夫。「音楽が好き、作曲家になりたい」という気持ちを重視しています。
中学校卒業以上であれば入学に年齢制限はなく、いつでも転入学・編入学可能です。中学校卒業後の一般的な4月の入学のほか、現在高校に通っている人も高校を退学した人も、転入学・編入学できます。
仙台と名古屋キャンパスは高等専修学校ですが、北海道芸術高等学校(通信制高校)とのダブルスクール制度を採用することで、全日制と同様の高校卒業資格の取得も可能となっています。そのため、卒業後の進路も大きく開かれていますので、心置きなく音楽に打ち込めます。
ボカロを含むDTMでの創作活動やバンド活動などで、音楽好きな仲間たちと楽曲作りの楽しさを追求しましょう。幅広い視点で音楽を学ぶことで、表現力や創造力を培いながら、時代が求めるスキルを身に付けることができます。

✅ 実際に芸高グループを卒業後、作曲家・編曲家として活動している先輩の声
『東北芸術高等専修学校では総合的に音楽を学べるのですが、僕はもともとダンスを習っていたこともあって、とくにDTM(パソコンを使った音楽制作)が面白くて大好きになりました。今の仕事にも役立っています。また、先生方はめちゃくちゃ協力的で、常に全面的にサポート&応援してくれました。技術面だけでなく、音楽業界でのコネクションの作り方だったり、人間関係の構築の仕方も教わりました。卒業後の仕事に繋がる機会を作ってくれたり、実際に業界の人に会わせてくれたりもしました。今は個人事務所に在籍し、作曲家・編曲家として活動しています。作曲や編曲にアレンジなど、東芸で学んで楽しかったDTMの仕事がメインになっています。今の僕の一番の収入源がDTMです。』
>もっと見る【卒業生インタビュー:Oさん】東芸で3年間学んだことは、現在の音楽の仕事において全て役に立っています!
✅ ミュージックコースに関するこちらの記事もチェック
> 高校から作曲家・シンガーソングライターなどプロのミュージシャンを目指すならミュージックコース/音楽科のある通信制高校がおすすめ
> プロ仕様の環境で学べる!施設・設備紹介(北海道芸術高等学校 札幌キャンパス編)生徒の口コミ・評判も!
好きなことだからがんばれる、一緒に歩んでくれる先生や仲間がいる。
芸高グループは、一人ひとりの個性や夢を応援してくれる場所です。
参照:北海道芸術高等学校 https://www.kyokei.ac.jp/
※本サイトは、芸高グループの生徒や先生にインタビューを行う機会をいただき、独自取材の記事で芸高グループを応援する個人運営サイトです。
> 生徒たちの様子がわかるInstagramはこちら
この記事をシェアする